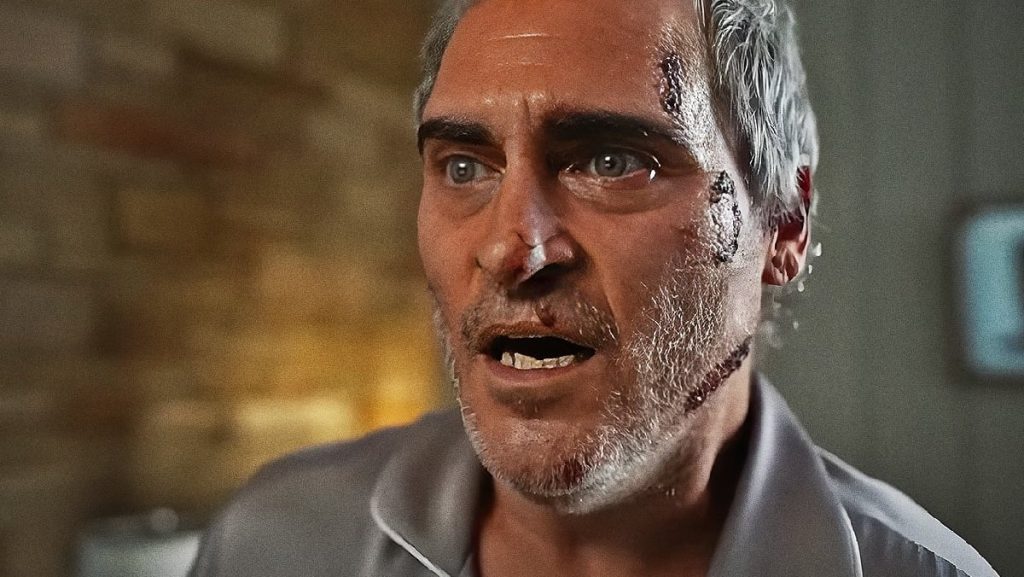監督:ローラ・ポイトラス
出演:ナン・ゴールディン
原題:All the Beauty and the Bloodshed
制作:アメリカ/2022
URL:https://klockworx-v.com/atbatb/
場所:MOVIXさいたま
まったく視野に入っていなかったローラ・ポイトラス監督の『美と殺戮のすべて』を知人から勧められてなんの情報も入れずに観てみた。
『美と殺戮のすべて』は、写真家ナン・ゴールディンの生い立ちやどのようなキャリアを積んできたのか、そして彼女自身も被害にあった医療用麻薬「オキシコンチン」による中毒蔓延の責任を追及する活動を追ったドキュメンタリーだった。
ナン・ゴールディンのことはまったく知らなかった。考えてみると画家や写真家には興味があるのだけれど、その人たちの情報を入れる窓口があまりにも狭すぎて、それなりに有名な人たちのことも知らないことが多い。この映画で知る限り、ナン・ゴールディンの写真は70年代のアングラっぽいイメージに見えて、撮った写真を自らスライドショーで構成するあたりは、むかし仕事で関わったことのある寺山修司をおもい出してしまった。
ナン・ゴールディンの生い立ちを追ううちに、彼女が大好きだった姉バーバラと母親との確執が見えてくる。母親は一方的にバーバラを統合失調症だと決めつけて施設に入れてしまう。その後、そこでバーバラは自殺してしまう。なぜ、姉は自殺したのか? を調べて行くうちに、精神を病んでいたのは姉ではなく母親ではなかったのか、が見えてくるのがミステリアスで、そこだけ掘り下げても面白いドキュメンタリーになっていたとおもう。でも、このドキュメンタリーの構成としては、複雑な家庭環境があったからこそナン・ゴールディンの過激な写真が生まれて来たとするもので、医者に「オキシコンチン」を処方されてしまうのもその流れの延長線上にあった。
で、この映画のもう一つの大きな柱としてはその「オピオイド鎮痛薬」の一種である「オキシコンチン」中毒が世の中に蔓延してしまった責任を製薬会社パーデュー・ファーマおよびその会社を支配するサックラー家を告発するナン・ゴールディンの活動だった。サックラー家は「オキシコンチン」で儲けたお金をさまざまな有名な美術館に寄付をしていた。そのため、たとえばメトロポリタン美術館ではデンドゥール神殿のあるエリアを「サックラー・ウィング」と名付けられ、ほかにもルーブル美術館やグッゲンハイム美術館など様々なところでサックラー家の名を冠しているものが数多くあった。ナン・ゴールディンたち「P.A.I.N.(Prescription Addiction Intervention Now)」と呼ばれる団体は、サックラー家の寄付を受けている美術館で抗議活動を行い、最終的に各美術館から「サックラー」の名前を外すことに成功する。
ナン・ゴールディンの姉のことからはじまったこの映画は、最後、姉についてで終わる。彼女の写真および抗議活動の源流には大好きな姉を失った「痛み」があったからこそだった。両親との折り合いが悪くなった「痛み」もあり、その後の既存のシステムに反発する「痛み」もある。ナン・ゴールディンがオピオイド危機に対抗するために作った団体「P.A.I.N.」は「オキシコンチン」中毒に対する「痛み」だけではなくて、ナン自身のすべての「痛み」も包括的に意味しているように見えてしまった。
たまには気にもとめていない映画を観るのもありだとおもう。まったく知らない世界と出会えるから。
→ローラ・ポイトラス→ナン・ゴールディン→アメリカ/2022→MOVIXさいたま→★★★★