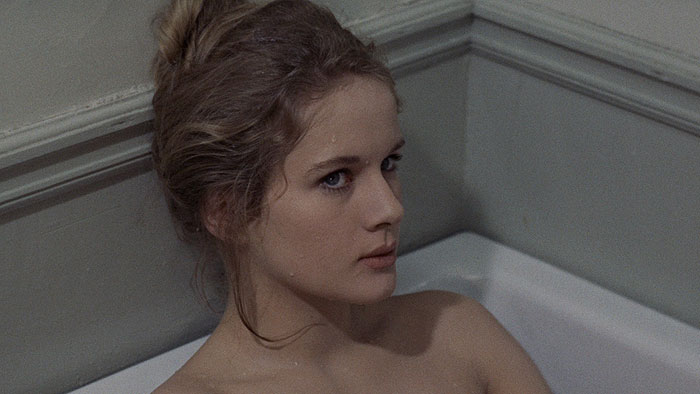監督:成島出
出演:藤野涼子、板垣瑞生、石井杏奈、清水尋也、富田望生、前田航基、望月歩、佐々木蔵之介、夏川結衣、永作博美、黒木華、田畑智子、塚地武雅、池谷のぶえ、田中壮太郎、市川美和子、高川裕也、江口のりこ、安藤玉恵、木下ほうか、井上肇、中西美帆、松重豊、小日向文世、津川雅彦、尾野真千子
制作:「ソロモンの偽証」製作委員会/2015
URL:http://solomon-movie.jp
場所:イオンシネマ板橋
うっかりしていて、もう少しで後篇を観るのを忘れるところだった。前、後篇に分けるのって、どうなんだろう。料金を高く設定してもいいから一気にすべてを観るほうがいいなあ。そんな上映方法は、今のシネコン時代では難しいのかもしれないけれど。
『ソロモンの偽証』を前、後篇とも見終わって、どうしても気になってしまうことが一つだけあった。それは、警察によって自殺と判断された少年の死が、ある告発状によって一人の不良少年に疑惑が向けられて、それが本当に不良少年の犯行なのかどうかを生徒たちによる学校内裁判によって裁かれる過程で、もうすでにその告発状が不良少年によっていじめられていた少女によって書かれた嘘で、少年の死が不良少年の犯行ではないことが映画の中でほとんど明確に示されているのに、不良少年の罪を問う生徒たちの裁判がストーリーの核となっている部分だ。
もうすでに興味の中心が不良少年の犯行かどうかではなくて、不良少年の弁護を担当する他校の生徒の正体なのに、不良少年の犯行当時のアリバイなどを問題視するのはまったくピントがズレてしまって、誰かはやく、このしたり顔の弁護人の正体を明らかにしろ! と云いたくなってしまった。
おそらく宮部みゆきの原作の構成がそうなんだろうけど、それを映画化する場合に、もうちょっと映画向けに再構成しても良かったんじゃないかとおもう。
→成島出→藤野涼子→「ソロモンの偽証」製作委員会/2015→イオンシネマ板橋→★★★☆