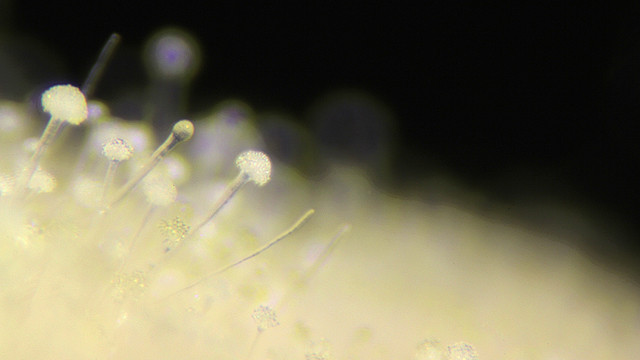監督:リドリー・スコット
出演:クリスチャン・ベール、ジョエル・エドガートン、ジョン・タトゥーロ、アーロン・ポール、ベン・メンデルソーン、マリア・バルベルデ、シガニー・ウィーバー、ベン・キングズレー、ヒアム・アッバス、アイザック・アンドリュース
原題:Exodus: Gods and Kings
制作:アメリカ、イギリス/2014
URL:http://www.foxmovies-jp.com/exodus/
場所:109シネマズ木場
高校の時の数学の先生が、授業の最中にセシル・B・デミル監督の『十戒』を熱く語っていたことを今でもおもいだす。理数系の勉強をして来ただろうとおもわれる数学の先生が、授業にはまったく関係のない『十戒』と云う宗教的な映画を語ることも可笑しかったし、紅海が真っ二つに割れるシーンを身振り手振りを加えて興奮して語る姿がめちゃくちゃ可笑しくて、今でも目に見えるようだ。
その先生の影響を受けてテレビではじめて『十戒』を見た。チャールトン・ヘストンのモーゼが呪文のようなものを唱えると、眼前に広がっている紅海が真っ二つに割れて海の底が見え、そこを歩いて渡って行くことが出来るようになるシーンは確かに凄かった。それは、CG技術の発達した最近の映画と比較すれば、子供だましの、ちゃんちゃら可笑しいシーンに見えるのだろうけれど、でも、モーゼの「出エジプト記」なんて神話のようなものなんだから、まるで昔の宗教画のようなタッチの絵がダイナミックに動いているからこそ感動したんだとおもう。
同じモーゼの「出エジプト記」を映画化したリドリー・スコットの『エクソダス:神と王』が、その紅海のシーンをどのように描いているのかとても気になった。クリスチャン・ベールのモーゼが紅海の前に立った時、さあ、どうなるんだ? と固唾を飲んで見守っていたら、紅海がパカッと真っ二つに割れると云うよりも、徐々に、時間を掛けて潮が引いて行く描写だった。うーん、リアリティを優先させれば確かにそうなるんだろうけど、何か違う。これでは「奇跡」に見えないじゃないか。メンフィスの町に天変地異が襲うシーンをリアルに描いても良いし、神の代弁をモーゼにしか見えない子供にさせるのも良い。でも、紅海のシーンは「奇跡」に見えなければいけなかったんじゃないのかなあ。
何でもCGでリアルに見せれば良いってものではないことがこの映画を見てよくわかった。特に、多くの人が知っている史実を描く時は、科学的根拠に基づくリアルさよりも、みんなの期待を優先させて描くべきだと云うことも。
→リドリー・スコット→クリスチャン・ベール→アメリカ、イギリス/2014→109シネマズ木場→★★★